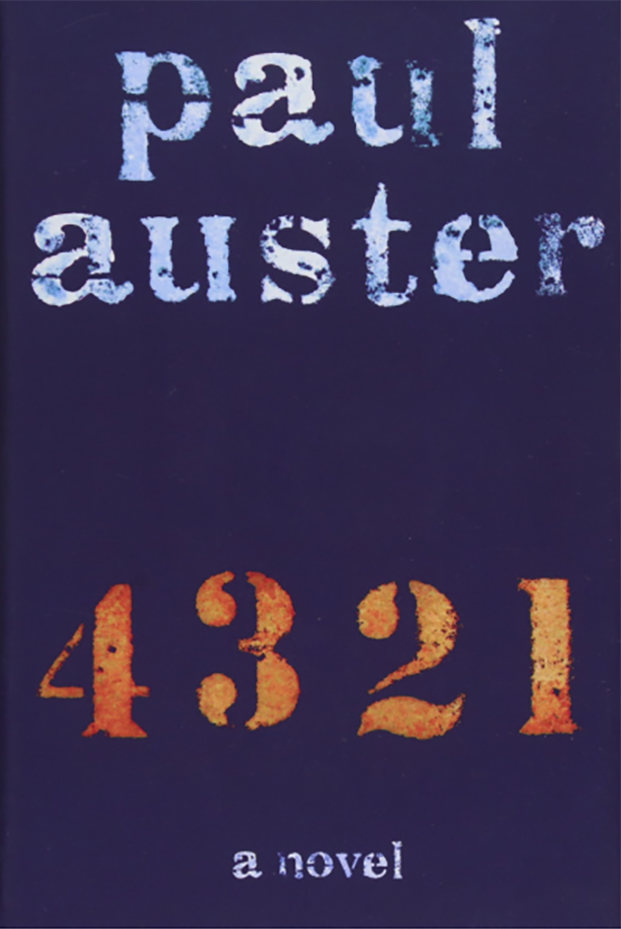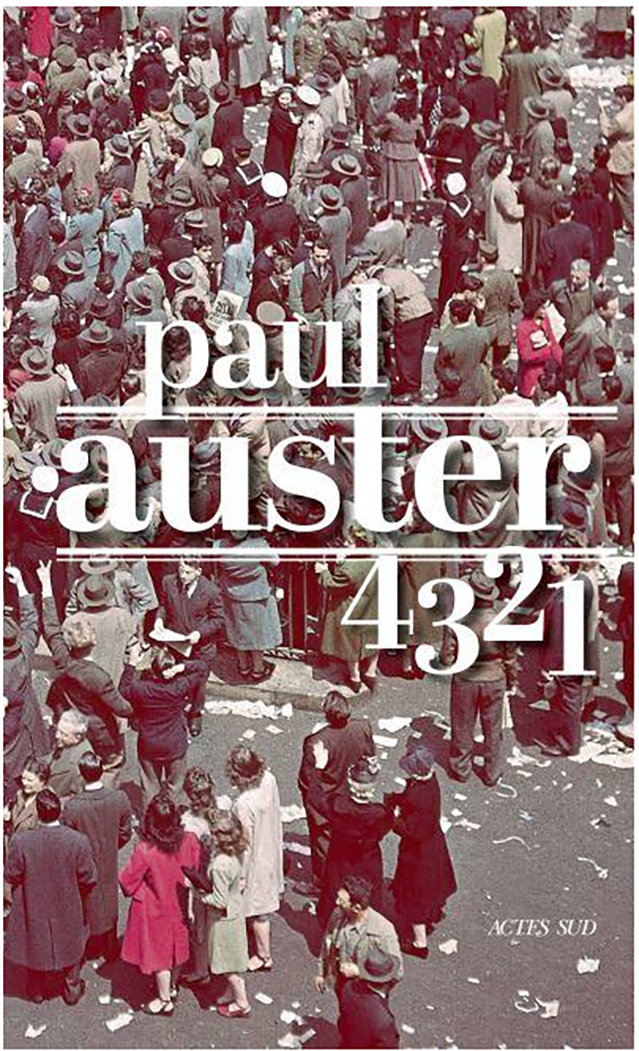北緯48度の読書日記/Lecture à latitude 48ºN 3
ポール・オースター(1947〜/アメリカ)
『4321』
「新しい本が出ればとりあえず読む」作家の一人にポール・オースターがいる。
彼の新作(原著は2017年刊)の仏語版が今年になって刊行された。この仏語版、ぱっと見がブロック(塀の)、1000ページ超のボリュームである。長編2冊と思えばたいしたことはないと読みはじめたが、そう単純なことでもなかった。
[フランス語版]
Paul Auster, 4321, Actes Sud (France), 2018.
Roman traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Gérard Meudal.
内容をひとくちにいえば、アーチー・ファーガソンという少年の成長物語である。この少年が青年期にいたるまでの4通りの人生が並行して語られる構成が、凝っているといえば凝っているところか。
基本的な出発点は同じで、ユダヤ系移民の孫として1947年ニューアークで誕生する。したがって各ファーガソンが成長する時代背景は共通するが、バージョンによって家庭環境や、興味の対象(スポーツ、映画、文学、政治、性的嗜好)が異なっていたり、本人が怪我や事故、事件に遭遇したりする。
いずれにしても、ニューヨークかその近郊の中産階級家庭の一人息子であることに変わりはなく、どのバージョンでもファーガソン少年は文学好きで、ものを書くことに秀で、ゆくゆくはジャーナリストか作家になるであろうと思わせる人物。しかも性格が共通して自意識が強く、ある種の人間(俗物や無教養な人間)にたいして拒絶、というか軽蔑をおぼえずにはいられないような、頑固で、悪くいえば、つまらないことに依怙地になるこのキャラクターが1000ページ続くと、読んでいてさすがに独裁圧政下にいるような、被害者めいた心もちがしてこなくもない。
この小説で語られるのはファーガソンの4つの分身――あるいは、オリジナルとその3つの分身――といえるが、成長する環境によって多少変化があらわれこそすれ、じつは同一の人格である。さらにいえば、オースターの過去の小説の主人公のだれかれをおのずと想起させる。
また、野球に熱中し、古い映画作品に人生の危機を救われ、フランスに恥ずかしいほど憧れ、ニューヨークに住むことにこだわる、等々のオースター作品に特徴的なモティーフが、4つのバージョンに分散されつつ描かれている。とりわけ「小説家への道を邁進バージョン」のファーガソンが書く小説(試作や構想も含め)は、オースター自身の過去のあれこれの作品に対応している。
こうしてみると、小説の主人公ファーガソンは作家オースター自身の投影にほかならない。そもそも、このふたりの生年と出生地が同じなのは露骨なくらいである。
オースターの最近の作品は「フィクション」を離れ、もっぱら「事実」とか「自分」に向かっていたような気がするが、そのすなおな延長として理解できる一方で、なにか後ろ向きというか、閉塞の度を増した世界でどこへも行きつけない戸惑い、発見や学ぶものがない恨みのようなものが残った。
たしかに70年代で終わるこの小説には、黒人差別問題や同性愛者の境遇が多く描かれていて、やや目先が変わっていたかもしれない。また、コロンビア大学の学生ファーガソンが巻き込まれる1968年の大学紛争も描写される。しかし、個人的につよく印象に残っている場面は、学生に暴力をふるう警官の目にファーガソンが憎悪を読みとるところだった。恵まれた学生に象徴されるブルジョワ、エリート、インテリへの劣等感、ねたみからくる純粋な憎悪。これはそのままファーガソン=オースターが警官(に象徴される人種、階級)にいだく優越意識と軽蔑の裏返しのようにも感じられ、なんとなく居心地が悪い。
たまたま前後して仏語版を読んだエジプト系米語作家、オマール=ロバート・ハミルトンの小説『The City Always Wins』はエジプトの「アラブの春」とその後をテーマとするが、ここに描かれる若者たちの切実さとの決定的な隔たりを感じずにはいられなかった。
Omar Robert Hamilton, La Ville gagne toujours, Gallimard (France), 2018.
Roman traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Sarah Gurcel.
Titre original : The City Always Wins.
しかし、わたしはなにも社会問題や現代性、リアリズムをもとめてオースターの小説を読んでいるのではない。むしろ、小説でしかありえない偶然や不思議な因果によって展開する世界、なんの変哲もない日常にふいに口をひらくパラレルワールド、些細なことから思いがけない方向へ転がっていく登場人物の運命――もちろん、それらは思わずつりこまれるオースターの筆致で描写されてこそ現実感と説得力をおびるのだが――、そんな小説を読む無条件の楽しみをもたらしてくれるのが、オースターの作品だった。